雲間草




霞立つ
古今集 - 在原元方
春の山辺は
遠けれど
吹きくる風は
花の香ぞする
雲間草
雲間草の育て方
置き場所
夏以外は日当たりと風通しのよい場所で育てます。寒さには強いのですが、暑さは少し苦手です。夏は風通しの良い半日陰などで管理しましょう。
屋外の場合
柔らかな風や、優しい雨は植物を十分にリフレッシュさせてくれます。夏は日差しが強く乾きの原因となるので注意が必要です。
「春・秋」
日当たりのいい環境で育成しましょう。特に春先はよく日光と風に当てることで元気で丈夫な葉になります。気温が高い時は半日陰や明るい日陰に移動しましょう。また、梅雨など、雨の続く時期は雨の当たらない場所に移して育成しましょう。
「夏」
基本的に明るい日陰などで育てます。よしずなどを用いて涼しい環境を整えてあげるのも良いでしょう。蒸れるのを嫌いますので、風通しが良いと理想的です。
「冬」
寒さには強いです。基本的には寒い場所で冬を体験させてあげましょう。屋外環境でも問題ありませんが、寒風や霜から保護しましょう。ムロや半屋内(寒い場所)などで管理することをオススメします。
屋内の場合
屋内で管理する場合、エアコンや暖房の風が当たる様な場所は避けましょう。偏った乾燥状態になり、植物は傷んでしまいます。たまに外の空気に当てたり、雨に当てたりしてあげると植物はリフレッシュでき元気に育ちます。
「春・秋」
出来るだけ風通しよく、日当たりのいい窓辺などで育成しましょう。
「夏」
夏は暑さで蒸れやすくなるので出来るだけ涼しい環境で育成しましょう。
「冬」
できるだけ寒い環境で育成しましょう。冬を体験することは非常に大切です。最低でも10~5℃以下になるような環境で管理しましょう。
水やり
自生地は高山の岩場などですから、基本的に用土は乾き気味の状態を好みます。水の与えすぎには注意しましょう。水やりの目安は、春秋は2日に1回、夏は2~3日に1回、冬は3~4日に1回です。しかしこれはあくまで目安ですので、観察しながら調整しましょう。環境によっても乾き方は違います。乾いていない時は与えないようにしましょう。
霧吹きなどでの葉水は好みますので、こまめに与えると元気に育ちます。
肥料
真夏を除く4〜10月は月に1~2回の頻度で液肥を与えます。
※バイオゴールドヴィコント564を基準にしています。その他の肥料を与える場合は説明書などを参考にしてください。
なお、春先の開花後は1カ月ほど「活性剤」のみ与えるようにしましょう。花が咲く木全般に共通しますが、開花後は少なからずストレスやダメージを受けています。その状態をケアする意味で活性剤のみ与えると樹勢が落ちず、健全な成長を助けることに繋がります。
病害虫
病害虫にとても強い樹木ですが、空気の乾燥が続くとハダニなどがつくことがあります。乾燥する時期は葉水をしておくと予防になります。
木々の小話
高山植物は難しい?
植物に詳しい方であれば、高山植物は育てるのが難しいというイメージがあるかもしれません。実際、日本自生の高山植物は平地での育成に向かないものが多いようです。(そもそも希少な種が多いので出回る機会が少ないのですが)
しかし、近年は西洋の丈夫な品種と交配され、育てやすい高山植物も増えました。石木花で扱う雲間草も西洋の雲間草と交配し、丈夫で育てやすい性質を持っているものを選抜しています。ですから、育てるのが難しいという事はありませんのでご安心ください。
高山植物は総じて寒さにとても強いものの、過度に暑い環境は嫌いますから夏は日陰の風通しのいい場所で「夏越し」させるなど、植物に優しい環境をつくってあげるとより元気に末永く育成することができます。
盆栽・多肉植物・サボテンなど、どんな植物でもその植物の性質にあわせた環境を整えてあげることが、末永く健やかに育成するポイントとなります。
雲間草の詳しいお手入れ
雲間草(くもまそう)に適した用土
一般には鹿沼土に軽石、桐生砂を混用したものを使用します。水はけの良い用土が最適です。
【石木花の土:酸性】 が適合します。
植え替え
時期は花が終わった直後から1か月以内がベストです。植え替え後はあまり暑くなったり乾燥したりしないように注意しましょう。また、小さい木は根を切り詰めないで一回り大きい鉢へ鉢増し(サイズアップ)した方が元気に育ちます。
雲間草(くもまそう)育成のポイント
◯基本的に日当りと風通りのいい場所で育成します。
◯いつもたっぷり湿っている状態を嫌います。やや乾かし気味の管理を心がけると元気に育ちます。
◯長雨に当てないようにしましょう。
◯肥料は定期的に与えましょう。花付き・生育が良くなります。
◯元気に育てるうえで活性剤は心強い味方になります。
肥料・活性剤
- 葉 Leaf
- 多数の芽が集まって群生しています。
- 花 Flower
-
4~5月、幻想的な花を咲かせます。
縁は赤く色づきます。
- 実 Seed
- 花後に実を付けます。
- 耐寒性 Cold
-
- 水やり Water
-
- 日光 Sun
-
- 肥料 Fertilizer
-
-
 万両 Sarcandra glabra
万両 Sarcandra glabra -
 深山カイドウ Malus micromalus
深山カイドウ Malus micromalus -
 トショウ Juniperus rigida
トショウ Juniperus rigida -
 猫の手シダ Rabbit's Foot Fern
猫の手シダ Rabbit's Foot Fern -
 ミズナラ Japanese oak
ミズナラ Japanese oak -
 ニワウメ Japanese bush cherry
ニワウメ Japanese bush cherry -
 姫オリーブ Little Ollie
姫オリーブ Little Ollie -
 錦糸ナンテン Nandina domestica var.capillaris
錦糸ナンテン Nandina domestica var.capillaris -
 桃色ユキヤナギ Fujino Pink Spirea
桃色ユキヤナギ Fujino Pink Spirea -
 ツリバナマユミ
ツリバナマユミ -
 タチマユミ
タチマユミ -
 トキワマンサク
トキワマンサク -
 銀葉シンパク
銀葉シンパク -
 イボタ Ligustrum obtusifolium
イボタ Ligustrum obtusifolium -
 沈丁花 Winter Daphne
沈丁花 Winter Daphne -
 サザンクロス
サザンクロス -
 スイレンボク
スイレンボク -
 ヤブデマリ
ヤブデマリ -
 姫ウツギ
姫ウツギ -
 フジ
フジ -
 コフジ
コフジ -
 オジギソウ
オジギソウ -
 姫ライラック
姫ライラック -
 コメツツジ
コメツツジ -
 ロウヤガキ
ロウヤガキ -
 連山ヒノキ
連山ヒノキ -
 サクランボ
サクランボ -
 キンズ
キンズ -
 シンパク
シンパク -
 エゾマツ
エゾマツ -
 コナラ
コナラ -
 リュウノヒゲ
リュウノヒゲ -
 椿
椿 -
 ナンテン
ナンテン -
 姫寒菊
姫寒菊 -
 津山ヒノキ
津山ヒノキ -
 斑入りヒイラギ
斑入りヒイラギ -
 緋ネム
緋ネム -
 雲間草
雲間草 -
 ネコヤナギ
ネコヤナギ -
 八房香丁木
八房香丁木 -
 木瓜
木瓜 -
 十月桜
十月桜 -
 キャラボク
キャラボク -
 天皇梅
天皇梅 -
 シロシタン
シロシタン -
 トキワサンザシ
トキワサンザシ -
 ヤブコウジ
ヤブコウジ -
 梅
梅 -
 長寿梅
長寿梅 -
 トキワシノブ
トキワシノブ -
 姫リンゴ
姫リンゴ -
 コムラサキ
コムラサキ -
 旭山桜
旭山桜 -
 富士桜
富士桜 -
 雲竜富士桜
雲竜富士桜 -
 イソザンショウ
イソザンショウ -
 姫シャクナゲ
姫シャクナゲ -
 コロキア
コロキア -
 しだれ桜
しだれ桜 -
 ゴヨウマツ
ゴヨウマツ -
 キバナジャスミン
キバナジャスミン -
 山ブドウ
山ブドウ -
 キンロバイ
キンロバイ -
 チリメンカズラ
チリメンカズラ -
 姫ネムノキ
姫ネムノキ -
 テイカカズラ
テイカカズラ -
 斑入りチリメンカズラ
斑入りチリメンカズラ -
 ヤマツツジ
ヤマツツジ -
 日向ミズキ
日向ミズキ -
 コプロスマ
コプロスマ -
 ヒメソナレ
ヒメソナレ -
 ツルウメモドキ
ツルウメモドキ -
 姫エンジュ
姫エンジュ -
 ヤマアジサイ
ヤマアジサイ -
 イチョウ
イチョウ -
 ヤマモミジ
ヤマモミジ -
 アカメシデ
アカメシデ -
 アセビ
アセビ -
 屋久島アセビ
屋久島アセビ -
 深山キリシマツツジ
深山キリシマツツジ -
 斑入りギンバイカ
斑入りギンバイカ -
 クロマツ
クロマツ -
 カマツカコケモモ
カマツカコケモモ -
 白鳥花
白鳥花 -
 香丁木
香丁木 -
 アベリア
アベリア -
 八房エゾマツ
八房エゾマツ -
 姫サルスベリ
姫サルスベリ -
 モミジバフウ
モミジバフウ -
 カラマツ
カラマツ -
 ナナカマド
ナナカマド -
 クチナシ
クチナシ -
 姫クチナシ
姫クチナシ -
 ニレケヤキ
ニレケヤキ -
 イタヤカエデ
イタヤカエデ -
 トウカエデ
トウカエデ -
 姫ヒイラギ
姫ヒイラギ -
 ノバラ
ノバラ -
 シラカシ
シラカシ -
 モミ
モミ -
 リョウブ
リョウブ -
 ヒメサカキ
ヒメサカキ -
 トドマツ
トドマツ -
 チャノキ
チャノキ -
 バレリーツリー
バレリーツリー -
 寒グミ
寒グミ -
 モチノキ
モチノキ -
 風知草
風知草 -
 ジャノメマツ
ジャノメマツ -
 アカマツ
アカマツ -
 ツクモヒバ
ツクモヒバ -
 トネリコ(アオダモ)
トネリコ(アオダモ) -
 ブナ
ブナ -
 シロヤシオ
シロヤシオ -
 クマヤナギ
クマヤナギ -
 キブシ
キブシ -
 カナシデ
カナシデ -
 クロモジ
クロモジ -
 夏ハゼ
夏ハゼ -
 マルバカエデ
マルバカエデ -
 金芽ケヤキ
金芽ケヤキ -
 ヤマドウタン
ヤマドウタン -
 エゴノキ
エゴノキ -
 ケヤキ
ケヤキ -
 ガマズミ
ガマズミ -
 ウリハダカエデ
ウリハダカエデ -
 ウチワカエデ
ウチワカエデ -
 まるうさぎ
まるうさぎ
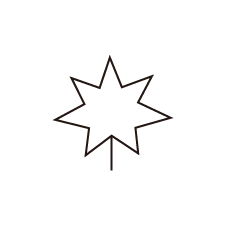
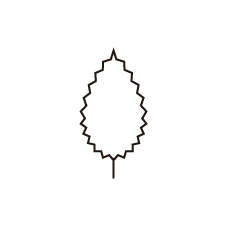
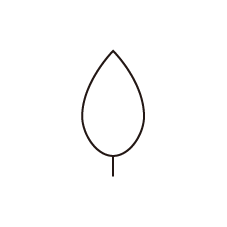

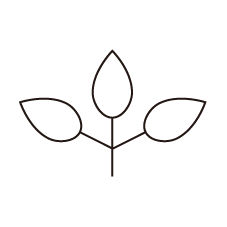
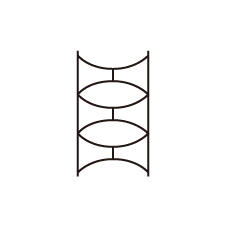






特徴的な名前は、「見つけるのが難しく、まるで雲の中にいるよう」であったり、「雲がかかる様な高い所で見つかる」ことに由来するそうです。