ツリバナマユミ




白真弓
万葉集 第十巻
今春山に行く雲の
行きや別れむ
恋しきものを
ツリバナマユミ
ツリバナマユミの育て方
置き場所
日当たりを好みます。
半日陰でも育てることができますが、日当たりがいい方が花や実の付きが良く、秋の紅葉も美しく色づきます。
屋外の場合
基本的に風通しのいい明るい日陰や、半日陰が適します。
特に新芽が伸び始める春先から梅雨頃まではしっかり日に当てることが大切なポイントです。
「春・秋」
日当たりと風通しの良い環境で育成しましょう。特に春は新芽が芽吹く大切な時期。しっかり日の光を浴びて広がった葉は丈夫に育ちます。
※春先、芽吹いたばかりの頃は夜間の冷え込みや霜で寒害になる可能性があります。夜間が冷え込むうちは日中は屋外で夜間は屋内にしまうなど工夫しましょう。
「夏場」
風通しのよい明るい半日陰で管理します。葉は強い日差しに弱いので、梅雨が明け夏の間は西日に当たらないようにしましょう。よしずや遮光ネットなどを用いて日陰をつくるのもオススメです。
「冬場」
自然界と同様に、しっかり冬を体験させる必要があります。屋外管理で問題ありませんが、寒風や霜からは保護しましょう。ムロや半屋内(寒い場所)などで管理することをオススメします。なお、落葉後は日光に当たらなくても特に問題ありません。
屋内の場合
屋内で管理する場合、風通しの確保が重要になります。たまに外の空気に当てたり、雨に当てたりしてあげると植物はリフレッシュできて元気に育ちます。エアコンの風が直接当たる場所や、直射日光が長時間当たるなど極度に気温の上がる場所は避けてください。
「春・秋」
窓辺など明るい場所で育成しましょう。特に春は新芽が芽吹く大切な時期。よく日光や風に当てることで、丈夫で健康的な葉になります。
「夏場」
優しい日当たりで風通しのよい場所で管理します。夏の強い直射日光は葉焼けの原因になるので、レースのカーテンなどで遮光してあげると良いでしょう。また、しめきった部屋では「蒸れ」によって痛んでしまう可能性がありますので、できるだけ風を通してあげると植物には優しい環境になります。
※室内育成の場合、小さな扇風機やサーキュレーターなどで優しい風を当ててあげるのも効果的です。常時風をあてるのではなく、リズム風や自然風に調整できるものがいいでしょう。
「冬場」
5℃以下の環境で冬を体験させる必要があります。11月~2月の間は屋外に近い環境で育成しましょう。マユミは落葉樹なので、寒さに触れると紅葉し、その後葉を落とします。落葉後は日光が当たらない環境でも問題ありません。
水やり
マユミは水の吸収が旺盛なタイプなので成長期の水切れに注意しましょう。水やりの目安は、春秋は1日1回、夏は朝夕の1日2回、冬は3日に1回ですが、乾いていない時は無理に水をあげる必要はありません。
みずやりのタイミング
また、暑い時期の葉水は、葉の乾燥防止や健康維持に効果的です。朝や夕方に霧吹き等で与えるといいでしょう。どうしても乾きやすい時期や外出時などは腰水という方法が有効です。
腰水について
肥料
マユミは肥料をよく好みますので3~5月頃と、暑さが和らぐ9~10月頃、週1回を目安に液肥を与えます。
※バイオゴールドヴィコント564を基準にしています。その他の肥料を与える場合は説明書などを参考にしてください。
※置き肥の場合は春と秋を中心に固形肥料を与えます。花後の結実する頃に肥料が効きすぎると実が落ちてしまうことがあるので、実をたくさん付けたい場合はこの時期には置き肥をのせないようにするとよいでしょう。
病害虫
基本的には病害虫には強いですが、春~秋はアブラムシやカイガラムシ、ハマキムシなどが発生することがあります。
→病害虫について
木々の小話
「真」の弓
マユミの枝は柔軟性があってよくしなり、古くは弓の材料として使われていました。数千年前の縄文時代前期の遺跡からもマユミの丸木弓が出土しています。他にも弓の材料としてカシやアズサ、ミズメ、ケヤキ、カヤ、イチイなどの木も使われていました。
真弓の名前に付いている「真」には、それそのものを表す、最高のもの、見事さをほめるなどの意味があります。このことから、数ある弓の素材のなかでもマユミが最もふさわしいものだということを表したのかもしれません。
現在では、その木肌の緻密で滑らかな材質から将棋の駒や印材などに使われています。また、しなりを利用してかんじきなども作られました。
春の恋歌
冒頭の歌は、いとしい女性と別れて旅立つ男の心情を詠んだもの。
白真弓
今春(いまはる)山に行く雲の
行きや別れむ
恋しきものを
訳:白真弓を張る、春の盛りの山に流れて行く雲のように
私はあなたと別れて行かなければならないのか
こんなに恋しくてならないのに
白真弓(しらまゆみ)とは白木のマユミで作った弓のこと。弓を張る・引く・射ることから、同音の「はる」「ひく」「いる」などにかかる枕詞。
万葉集では弓の形状を連想させる歌が多いなか、この歌の洒落ている部分は「(弓を)今張る」を「今春」にかけて掛詞としても意味を持たせているところ。白真弓を「春」にかけている和歌は、この歌のみと言われています。
青々とした春の山にたなびく雲を見つめ、恋しさを募らせながら旅路を行く。春の霞んだ景色のように切ない情景が浮かびます。
ツリバナマユミの詳しいお手入れ
マユミに適した用土
基本的には赤玉土を主体に鹿沼土などを混ぜた混合土を使用します。
【石木花の土】が適合します。
植え替え
マユミは根の生長が早いため1年で鉢内に細根が充満します。根詰まりを起こしやすくなるので若木、成木ともに1~2年に1回を目安に植え替えるとよいでしょう。適期は春の芽出し前(3月上旬くらい)か秋口(9月中旬~下旬)。
マユミは細根タイプなので、残す根っこを傷めないように周りの土を優しく落とします。1/3ほどをほぐして細い小根をできるだけ多く残します。太い根は残さずに元の方から切除しましょう。
剪定
マユミは実のなった跡に葉芽がなく、先のほうにしか葉芽をもたない傾向があります。そのため、毎年実をつけると枝が間伸びしてしまいます。実を付けるのは1~2年おきにして木を休ませ、間の1年は芽摘みや剪定で樹形を整えるようにします。
芽摘みは5月頃が適期。2節(葉4枚)を残してカットします。すると葉っぱの脇から2番芽が伸び枝数が増えます。
樹形を整える剪定は休眠期に行いますが、全体を切り詰めると花芽を失うことになるので短枝を残し、長く伸びた枝のみを間引きます。剪定跡は「切口被覆塗布材」を塗って保護しておくと安心です。
切口被覆塗布材|カットパスターペースト
マユミ育成のポイント
○植物に四季を体感させてあげることで末永く健康的に育成できます。特に冬はしっかり休ませてあげましょう。
○夏は直射日光を避けた、明るい日陰や半日陰で管理します。よしず等で日陰を作るのもいいでしょう。
○小さな鉢で育成する場合、水切れさせないように注意します。特に夏場は、朝に水をやっても夕方乾いてしまう様なら置く場所を工夫し、出来るだけ涼しい所で管理しましょう。どうしても乾いてしまう場合には、腰水で凌ぎます。※日々の育て方をご参照ください。
○暑い時期や乾燥する時は、朝や夕方に葉水をするのも大変効果的です。
○屋内管理の時間が長いと、徐々に元気がなくなってしまいます。できるだけ自然の風に当てて育てるよう心がけましょう。雨の日は外に出して雨に当ててあげたり、夜は夜露に当てたりするとリフレッシュできます。
○室内育成の場合、小さな扇風機やサーキュレーターなどで優しい風を当ててあげるのも効果的です。常時風をあてるのではなく、リズム風や自然風に調整できるものがいいでしょう。
○活性剤を定期的に与えることで、より健やかに育成できます。
- 葉 Leaf
-
楕円形で葉縁は細かい鋸葉をつけます。秋にはオレンジや赤色に色づきます。
- 花 Flower
- 晩春から初夏に、淡い緑色あるいは薄紫色の小さな花を咲かせます。
- 実 Seed
- 四角い薄紅色の実がつき、熟すと仮種皮が5つに裂けて中から深紅の実を覗かせます。
- 耐寒性 Cold
-
- 水やり Water
-
- 日光 Sun
-
- 肥料 Fertilizer
-
-
 深山カイドウ Malus micromalus
深山カイドウ Malus micromalus -
 トショウ Juniperus rigida
トショウ Juniperus rigida -
 猫の手シダ Rabbit's Foot Fern
猫の手シダ Rabbit's Foot Fern -
 ミズナラ Japanese oak
ミズナラ Japanese oak -
 ニワウメ Japanese bush cherry
ニワウメ Japanese bush cherry -
 姫オリーブ Little Ollie
姫オリーブ Little Ollie -
 錦糸ナンテン Nandina domestica var.capillaris
錦糸ナンテン Nandina domestica var.capillaris -
 桃色ユキヤナギ Fujino Pink Spirea
桃色ユキヤナギ Fujino Pink Spirea -
 ツリバナマユミ
ツリバナマユミ -
 タチマユミ
タチマユミ -
 トキワマンサク
トキワマンサク -
 銀葉シンパク
銀葉シンパク -
 イボタ Ligustrum obtusifolium
イボタ Ligustrum obtusifolium -
 沈丁花 Winter Daphne
沈丁花 Winter Daphne -
 サザンクロス
サザンクロス -
 スイレンボク
スイレンボク -
 ヤブデマリ
ヤブデマリ -
 姫ウツギ
姫ウツギ -
 フジ
フジ -
 コフジ
コフジ -
 オジギソウ
オジギソウ -
 姫ライラック
姫ライラック -
 コメツツジ
コメツツジ -
 ロウヤガキ
ロウヤガキ -
 連山ヒノキ
連山ヒノキ -
 サクランボ
サクランボ -
 キンズ
キンズ -
 シンパク
シンパク -
 エゾマツ
エゾマツ -
 コナラ
コナラ -
 リュウノヒゲ
リュウノヒゲ -
 椿
椿 -
 ナンテン
ナンテン -
 姫寒菊
姫寒菊 -
 津山ヒノキ
津山ヒノキ -
 斑入りヒイラギ
斑入りヒイラギ -
 緋ネム
緋ネム -
 雲間草
雲間草 -
 ネコヤナギ
ネコヤナギ -
 八房香丁木
八房香丁木 -
 木瓜
木瓜 -
 十月桜
十月桜 -
 キャラボク
キャラボク -
 天皇梅
天皇梅 -
 シロシタン
シロシタン -
 トキワサンザシ
トキワサンザシ -
 ヤブコウジ
ヤブコウジ -
 梅
梅 -
 長寿梅
長寿梅 -
 トキワシノブ
トキワシノブ -
 姫リンゴ
姫リンゴ -
 コムラサキ
コムラサキ -
 旭山桜
旭山桜 -
 富士桜
富士桜 -
 雲竜富士桜
雲竜富士桜 -
 イソザンショウ
イソザンショウ -
 姫シャクナゲ
姫シャクナゲ -
 コロキア
コロキア -
 しだれ桜
しだれ桜 -
 ゴヨウマツ
ゴヨウマツ -
 キバナジャスミン
キバナジャスミン -
 山ブドウ
山ブドウ -
 キンロバイ
キンロバイ -
 チリメンカズラ
チリメンカズラ -
 姫ネムノキ
姫ネムノキ -
 テイカカズラ
テイカカズラ -
 斑入りチリメンカズラ
斑入りチリメンカズラ -
 ヤマツツジ
ヤマツツジ -
 日向ミズキ
日向ミズキ -
 コプロスマ
コプロスマ -
 ヒメソナレ
ヒメソナレ -
 ツルウメモドキ
ツルウメモドキ -
 姫エンジュ
姫エンジュ -
 ヤマアジサイ
ヤマアジサイ -
 イチョウ
イチョウ -
 ヤマモミジ
ヤマモミジ -
 アカメシデ
アカメシデ -
 アセビ
アセビ -
 屋久島アセビ
屋久島アセビ -
 深山キリシマツツジ
深山キリシマツツジ -
 斑入りギンバイカ
斑入りギンバイカ -
 クロマツ
クロマツ -
 カマツカコケモモ
カマツカコケモモ -
 白鳥花
白鳥花 -
 香丁木
香丁木 -
 アベリア
アベリア -
 八房エゾマツ
八房エゾマツ -
 姫サルスベリ
姫サルスベリ -
 モミジバフウ
モミジバフウ -
 カラマツ
カラマツ -
 ナナカマド
ナナカマド -
 クチナシ
クチナシ -
 姫クチナシ
姫クチナシ -
 ニレケヤキ
ニレケヤキ -
 イタヤカエデ
イタヤカエデ -
 トウカエデ
トウカエデ -
 姫ヒイラギ
姫ヒイラギ -
 ノバラ
ノバラ -
 シラカシ
シラカシ -
 モミ
モミ -
 リョウブ
リョウブ -
 ヒメサカキ
ヒメサカキ -
 トドマツ
トドマツ -
 チャノキ
チャノキ -
 バレリーツリー
バレリーツリー -
 寒グミ
寒グミ -
 モチノキ
モチノキ -
 風知草
風知草 -
 ジャノメマツ
ジャノメマツ -
 アカマツ
アカマツ -
 ツクモヒバ
ツクモヒバ -
 トネリコ(アオダモ)
トネリコ(アオダモ) -
 ブナ
ブナ -
 シロヤシオ
シロヤシオ -
 クマヤナギ
クマヤナギ -
 キブシ
キブシ -
 カナシデ
カナシデ -
 クロモジ
クロモジ -
 夏ハゼ
夏ハゼ -
 マルバカエデ
マルバカエデ -
 金芽ケヤキ
金芽ケヤキ -
 ヤマドウタン
ヤマドウタン -
 エゴノキ
エゴノキ -
 ケヤキ
ケヤキ -
 ガマズミ
ガマズミ -
 ウリハダカエデ
ウリハダカエデ -
 ウチワカエデ
ウチワカエデ -
 まるうさぎ
まるうさぎ
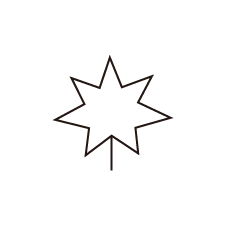
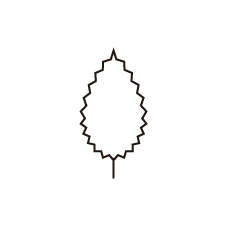
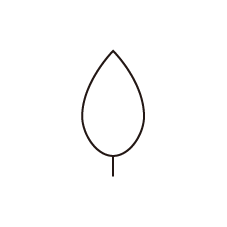

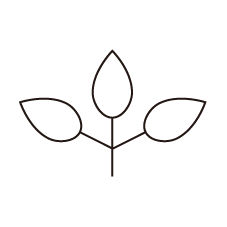
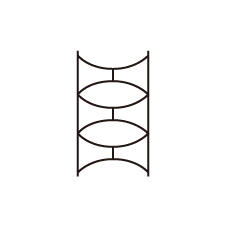






秋には薄紅色の果実が四角く膨らみ目を奪われる。
さらに晩秋には実を包んでいる皮が割れて真っ赤な種子が顔を出し、これがまた可愛らしい。
耐寒性、耐暑性があり丈夫な性質で育てやすい樹木です。